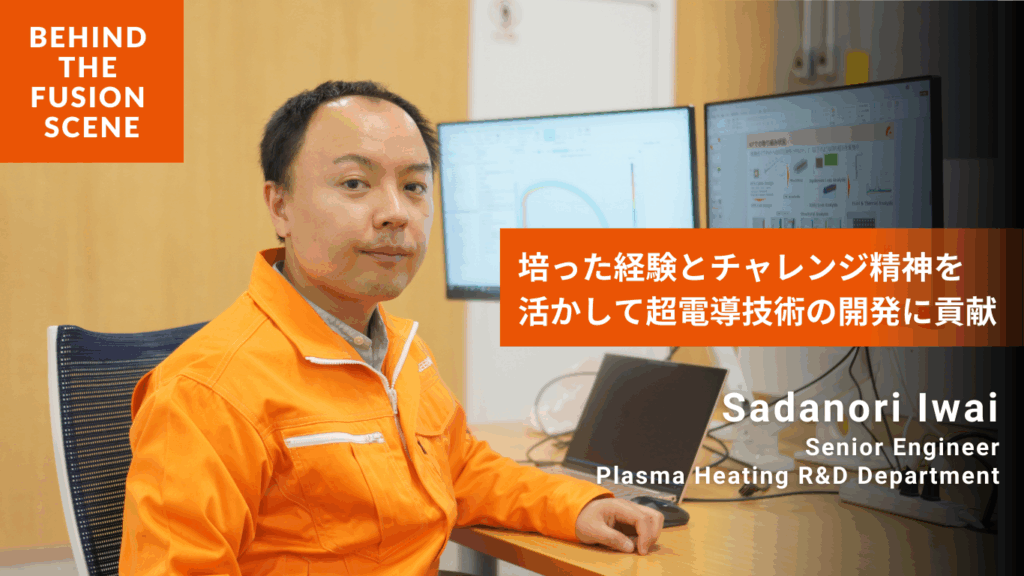
In a nutshell:
2023年7月に電磁工学エンジニアとして京都フュージョニアリング(KF)に入社した岩井さん。KFの主要領域である「ジャイロトロンシステム」に用いられる超電導マグネットや、英国原子力公社(UKAEA)向けの試験用高温超電導(HTS)マグネットの開発など、超電導領域のエキスパートとして様々なプロジェクトで活躍しています。
岩井さんは現在、電磁工学エンジニアとして活躍されています。もともとこの分野に興味をお持ちだったのでしょうか?
物理学に興味を持ったのは、高校生のときです。大阪大学でPhD.を取得した先生が担当していた物理の授業がきっかけでした。
先生の授業は、教科書の内容にとどまらず、身近な現象をわかりやすく解き明かしてくれる授業で、その面白さに私はどんどん引き込まれていきました。「この現象は、対象にどのような原理で、どのような力を及ぼすのか、どのような変化をもたらすのか?」といったメカニズムを深く知る面白さに目覚め、大学でも物理学を専攻することに決めました。
大学では、物質の性質をもっと深く学びたいと考え、物性物理の研究室を選びました。そこで出会ったのが、超電導技術にも関連する「極低温物性物理」でした。
マイナス何百度という想像もつかないほどの極限環境では、ある物質がまるで別の物質に変わったかのような特性を持つ。そんな世界にすっかり魅了されていました。
そして、大学院修了後は、研究で得た極低温物性物理の知識を社会に生かしたいという思いから、極低温・超電導技術を扱っている電機メーカーに就職しました。
大学院終了後に就職したメーカーでは、どのような業務を担当していましたか?
そこでは15年以上にわたり、超電導技術の基礎開発から製品化まで、幅広い工程に携わることができました。超電導の分野は歴史こそ長いものの、製品として実用化するには多くのハードルがあります。私たちは製品部門や技術部門の垣根を越えて、「どんな製品だと、超電導技術を生かせるのか?」「どのような設計なら製品として実現が可能か?」を議論しながら、研究開発されてきた技術を製品に落とし込んでいきました。
岩井さんがエンジニアとして経験を積む中で、特にご自身の成長につながったと実感した経験はありますか?
印象に残っているのは、会社の上司の後押しのもと、個人で仕事を続けながら電気電子工学のPhD.を取得したことですね。エンジニアとしてPhD.を取得する必要はありませんでしたが、一研究者としての姿勢・視点も身につけて思考の幅を広げたいと考え、博士課程に挑戦することにしました。
何か新しいことを学問として学び、研究を通じて理解を深めるというよりは、業務で得た技術や知見を体系的に整理し、論文にまとめる作業が中心でしたが、点在していた知識が一本の線でつながり、「全体像」を見渡せるようになったのは大きな収穫でした。
例えば、製品開発において「目的→機能→設計→製造」という一連の流れを意識できるようになり、どの段階で何が課題になるかを事前に予測できるようになりました。

メーカーで経験を積んだ岩井さんが、核融合業界への転職を決めた背景について教えてください。
実は、就職活動をしていたころからフュージョンエネルギーには興味がありました。超電導技術の応用先を調べていたとき、フュージョンエネルギーが未来のエネルギー源として紹介されているのを見つけ、スケールの大きさに衝撃を受けたのを覚えています。
このときに感じたワクワク感は、新卒で入社する会社を選ぶときにも影響を与えました。実際、入社した電機メーカーではフュージョンエネルギー技術の開発にも力を入れていたので、採用面接で志望理由を話すときにも、フュージョンエネルギーについて言及するくらい関心が強かったです。
メーカーで働いていたときは、直接フュージョンエネルギーに関わる機会はなかったものの、社内でプロジェクトの進捗やマイルストーン達成のニュースが届くたびに、フュージョンエネルギーの技術開発が進んでいることへの期待が高まっていました。
その後、メーカーで一通りの経験を積む中で、次のキャリアを考えるようになりました。ひとつは、今いる会社でマネジメント業務に従事する道。もうひとつは、別の企業でエンジニアとしてさらに専門性を高める道。エンジニアとしてさらなる成長を求めていた私は、迷わず後者を選びました。そして、ずっと心にあった核融合業界に挑戦し、一流のエンジニアとして活躍したいと強く思うようになりました。
そして核融合業界で電機工学エンジニアとして活躍できる場所を探す中で、KFを見つけました。ディープテックでありながらも、日本のものづくり力を積極的に海外に展開し、ジャイロトロンシステムの販売実績がある点には驚きました。ほかにもスピード感をもって技術開発を取り組んでいる点や、業界で著名な方が在籍している点などを考慮し、「KFなら、製品のための技術開発を通じてさらに自分の領域を広げられそう」と感じ、応募を決意しました。
KFに入社以降、どのような業務に取り組んでいますか?
Plasma Heating Divisionに所属し、電磁工学エンジニアとして超電導マグネット(SCM)や次世代の高温超電導(HTS)マグネットの仕様検討に取り組んでいます。
プラズマ加熱装置「ジャイロトロンシステム」において、当社は顧客のニーズに合わせた性能を備えたジャイロトロンシステムを納品するため、機器の仕様を都度調整する必要があります。私が担当しているSCMは、磁場を通じてジャイロトロン本体はもちろん他の機器にも影響を及ぼすので、他の機器を担当しているメンバーと密に連携し、協力会社とも何度も仕様について認識をすり合わせながら、技術開発を進めています。
さらに、英国原子力公社(UKAEA)が推進する「STEP(Spherical Tokamak for Energy Production)」向けのHTSマグネットの研究開発も担当しています。このプロジェクトは、STEPに組み込まれるHTSマグネットの設計・解析・製造する上で必要となる超電導コイルの実データの取得や、本データを活用したマグネットデザインの高度化を主な目的としたもので、HTS線材の領域で強みを持つフジクラ社と、フュージョンプラントのエンジニアリングのノウハウを持つKFとが連携し、プロジェクトを推進しています。
プロジェクトマネージャーの西村さんとともに、常にプロジェクト全体を俯瞰しながら、ステークホルダーとも連携してプロジェクトを進めてきました。
UKAEAがイメージしている目標を聞き出し、社内でそれを実現するうえで必要な項目を洗い出します。当社が検討した方針をフジクラ社に伝えてレビューを重ねながら試作品の製造を行いました。言語の違いもあって大変なときもありますが、これまで私が培ってきた技術力や、PhD.を取得する中で培ってきた課題解決のフレームワークを存分に発揮できていると思います。
実際にプロジェクトを進める上でUKAEAからポジティブなフィードバックを貰えており、このプロジェクトに携わることができていることに喜びを感じています。

岩井さんが今後、KFおよび核融合の領域で実現したいことを教えてください
超電導技術を扱う電磁工学エンジニアとして、フュージョンエネルギー用のHTSマグネットやSCMの実用化を実現したいと考えています。引き続き乗り越えなければならない技術的な課題はありますが、社内の経験豊富なメンバーや、日本の優れたものづくり企業の皆さまと力を合わせれば、核融合炉に適したSCMを開発できると信じています。
KF内では毎日新たな挑戦が押し寄せ、目が回るような忙しさに包まれることもあります。それでも、私は超電導のような「極限状態」にこそワクワクする性分なので、これまで培ってきた技術に、周囲の皆さんの知識や知見を融合させながら、フュージョンエネルギー実現という壮大な挑戦を楽しみ、前進していきたいと思っています。




